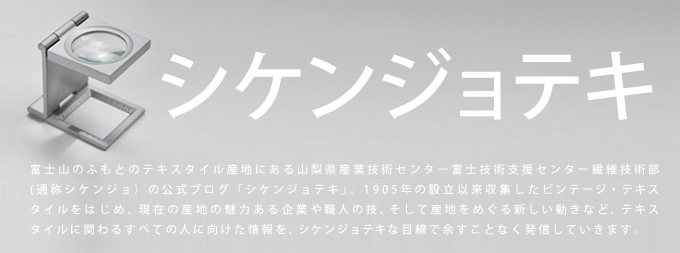明治~昭和初期の文学に描かれた甲斐絹を紹介するシリーズ、第5回。
今回はその名も『甲斐絹』という短編小説それ自体をご紹介したいと思います。
小説『甲斐絹』は、母親想いのヒロイン、園子が、甲斐絹に関連した大ピンチから脱出しようと奮闘する物語です。
タイトルがズバリ『甲斐絹』そのものという記念碑的な作品なのに、写真にあるように文語体で書かれているため、読みづらいというのがもったいない作品です。
そこで、シケンジョテキでは、今回新たに全文を現代語訳してお送りします!
長さは文庫本で10ページ分くらいです。「かみ、なか、しも」の3部構成になっています。
それではぜひどうぞお読みください。
落合直文作『甲斐絹』現代語訳、はじまり、はじまり。
『甲斐絹』 落合直文:著 (現代語訳版)
かみ
しぐれ、みぞれ、霰。空は冬の寒さである。昨夜からは雪まで降りはじめた。貧しい家ではよく眠れずに夜を明かしたことだろう。少女は朝早く起きて戸を開けた。垣根のあたりはみな雪に埋もれてしまって、さざんか、寒梅などの枝先も見わけられなかった。
この少女というのは早瀬家の娘で、名を園子という。性格はとてもおだやかで、容姿もすぐれた娘であった。父との別離のあとで生活はとても苦しかったが、母の温情からとある女学校に通うことができ、去年の秋にそこを卒業したばかりである。しかし近頃、その母が病にかかってからは、日夜看病をして過ごすようになっていた。
あるとき咳をする声が聞こえ、母が目を覚ましたことを知った園子は急いで部屋に向かった。枕もとに手をついて、園子は言った。
「おめざめですか。今朝は雪も降って、寒さもこらえきれないほどです。お気分はいかがでしょう。」
そう問うと母は
「変わりありません。」
と答える。また母が
「竹村様からお返事はありませんか。」
と問うと園子は
「昨夜おそくありました。すぐにもお見せしようと思いましたが、よくお眠りになっていたので、そのままにしておりました。」
と言い、懐から取り出した。母は手に取り、半分くらい読んだところで、とてもうれしそうな表情になり
「園、あなたの就職先があるそうですよ」
と言ってまた読む。母は
「竹村様はあなたにすぐ来るようにと。すぐにお行きなさい。」
と言う。園子が
「お母さまのご病気をほうっては。」
と言うと、母は言った。
「心配いりません。女中のお染がいればなんとかなります。」
「でしたら、行って参ります。」
「今日は大事な日です。気を引き締めて間違いのないようになさい。親戚に顔向けできぬことなどないように、人さまに後ろ指を指されることのないように。」
園子は出て行った。積もった雪を踏みわけつつ、母の愛情の深さをかみしめながら。
一月四日のことだった。雪こそ積もっていたが、世間は年初めであったので、いたるところで門松を立て、しめ縄を引き張り、手まり、羽根つきなどに興じている。竹村家に着くと、新年のあいさつ客があるとみえ、屠蘇に酔い、歌い舞うさまは、たとえようのない賑やかさである。園子は心のうちに母のことを思い出し、世の中はいろいろなのだなと複雑な心境になるのだった。
玄関で案内を請い、家に上がって主人に会った。主人は竹村早雄といい、堅実さでよく知られ、そのころ成功者としてよく知られた人物であった。年は六十を二つ三つ越えたくらい、頭髪はやや白かった。彼は園子にむかって
「母君の頼みで、あなたを教員にしようと思っている。英語そのほかの学問は充分だろうが、裁縫はどうかね。」
と問うた。園子は
「ふつつかながら、おおよそのところは。」
と答える。主人は
「ある県で知事をしている友人がいる。とくに女性教員を採用したいそうで、今回は裁縫に詳しい人をとの仰せだ。一、二週間も我が家で過ごし、それから伝えようと思うが、どうかね。」
という。園子は母の病気のことが気にかかったので
「母に聞いたのちにお返事いたしたく存じます。」
と答えて帰宅した。
首を長くして帰りを待ちわびていた母は、園子が戻るとすぐにその仔細を尋ね、園子はありのままを答えた。園子は
「今はどうにもなりません。待っていればまた良いお話があるでしょう。母上のご全快を待ってからでも。」
と言った。母はそれを聞きいれず、
「あなたの進路が定まるのならば、この身がどうなろうとそれが定めです。いつかは誰にも別れはやってくるのですよ。母のことなど気にせずに。どんなときにも、いまの母のことばどおりに。」
と言った。園子は
「そのお気持ちはごもっともですが。」
「この母のためと思って。」
「それでも。」
「何度くりかえしてもしかたがありません。早くお行きなさい。」
そういう母の声は少し怒っているようだった。園子は返す言葉もなく、少ししてから
「ともかく明日にいたしましょう、今日はもう遅いですから。」
と母に言った。
園子は母の性格を知っていたので、もう一度繰り返してしまえば病気にもさわり、心を痛めるだろうと思い、仕方なく言うとおりにした。そして女中を呼び、薬のこと、医者のこと、食べ物のことなど詳しく言い聞かせ、後ろ髪を引かれながら出て行った。
なか
園子は年が明けて十七となっていた。母を想う心ふかく、母を想わぬときはなかった。竹村家にいるのも母のためであり、家に帰らずにいるのも母を想ってのこと、母を喜ばせたいからである。一事が万事、母のためなのであった。身体を大事にするのも母があってこそ、わが身の出世を願うのも母があってのことであった。要するに、園子の心には母を想うこと以外になにもないのであった。この健気な母親想いの娘を神は守って下さるであろうか、この哀れなる孝行娘のことを神はご存じなのであろうか。
ある日の夜、主人が園子を呼び、一巻きの甲斐絹を手渡し、
「これを裁断し、私の寝衣を作ってくれんか。」
と言う。園子は
「承知いたしました。」
と答えて受け取った。園子は心の中で、これは私を試そうとなさっているのだ、母からの忠告はこの時のためにあったのだと悟ると、その部屋を辞し、灯りの元で生地を裁ち切った。するとなんという失態であろうか、違うところを切ってしまった。ああ、と驚いたときには、もう為すすべはないのだった。どうにかしなければと思い悩めば、その脳裏に浮かぶのは母のことであった。裁ちそこなってしまった絹の上には数えきれない涙の粒が落ち、その夜は一晩泣き明かした。
翌朝すぐにその絹の生地を携えて、大丸へ行って問い合わせたが、在庫はないという。越後屋、白木屋にも訪ねたが、そこも同じであった。
ほかにどうしようもなくなってしまい、母に相談してみようと家に帰ることにし、急ぎに急いで門のところまでやって来た。とはいうものの、さすがに入りづらく、行きつ戻りつしたあげく、とうとう家には入ることができなかった。
竹村家に帰ったけれど、あやまちが露見しないだろうか、日数がかかりすぎてしまうのでは、と心は乱れた。風邪をひいたと偽って園子は床についた。嘘をつくのは悪いことだ。悪いということは園子も知ってはいたけれど、でもそれはわが身かわいさからではなく、母のためなのだった。園子の嘘は、偽りとはいえども、真実にもまさる誠の心から生まれたものといえただろう。
一日二日すぎて、竹村の妻、玉江が園子の部屋に入ってきて
「おかげんはいかが。」
と問う。園子は
「ありがとうございます。なんとか良いほうです。」
と答える。玉江は
「薬でもお飲みなさい。」
と勧める。園子は
「それほどではございません。ところで、ご主人さまの御召物が遅くなってしまい申し訳ありません。少し良くなったら縫いますので、よろしくお伝えくださいますか。」
という。玉江は
「それは別の者にも頼めましょう。ただあなたの病気が。」
「その御召物はぜひ私が。」
そして園子は言葉を重ねた。
「あの反物は縞柄、風合い、とても美しいものでした。どちらからご入手されたものでありましょうか。」
玉江は
「お歳暮にと、水谷様という御方からいただいたものですよ。」
「水谷様とは、どちらの御方でしょうか。きっとお国元で作られた織物なのでしょう。」
「水谷様も、よそからお求めになったものだそうです。」
「水谷様は、私がこちらに参ってからはお越しになられていないようですが、いかがでしょう。」
「時折お見えになりましたが、近頃は学校も始まり、いまは大学の寄宿舎におられるかと。」
そのように何気なく質問をかさねるうち、園子は水谷という御方のことを知り、またその所在さえも聞くことができた。園子の喜びようといったらなかった。園子は心の中でひとり思った。水谷様は見も知らぬ御方なので、いきなりお手紙でお願いするというのはいかがなものだろう。また手紙では心からの思いをお伝えすることも難しい。お目にかかり、直にお願いさせていただこう。そうよ、そうすることにしよう、と思い定めたけれど、どんな御方なのかも分からないのでは、言い出したはいいが恥をさらすことになりはしないだろうか。そうなっても仕方のないこととはいえ、どうしたものか、と何度も思い返しては、繰り返し考え直すのだった。
しも
煉瓦づくりの建物が建ち並び、松の木なども所々に植えられて、目にも広々としたその場所は、くだんの学校であった。意を決した園子は、恐れる様子もみせずに進み入り、呼び鈴を鳴らして案内を乞うと、係の者が現れた。名刺を渡して水谷氏への面会を求め、応接室に通されて、待つこと二十分あまり。そのあいだ園子は終始うつむいて、物思いにふけっていた。どのような順序で話すべきかと考えていたのであろう。
水谷は名刺を受け取ったものの、まったく知らない人物で、しかも女性。いったいどういうことだろう、と不審に思いながら部屋に入って来た。それに気づいた園子は椅子から立ち上がって一礼すると
「大変ご無礼とは存じますが、実はお願いしたいことがありまして参りました。ここでは差し支えがあろうかと存じますので、しばし外へご一緒いただけますでしょうか。」と言う。
いよいよ妙なことになってきたと思いつつも、お願いごとと聞いては断りづらく、水谷も一緒に席を立った。
門には二台の車があり、片方に水谷を乗せて先に走らせ、園子は少し間をおいて後を追った。車は上野の方へと進んで行く。水谷は振り返りもせず、園子もそちらを見ることはなかった。不忍池のほとりで車を停めると、園子は水谷をとある茶店の奥へ伴った。園子が手をついて、なにかを言おうとして言えずにいる様子をみて水谷はこう言った。
「お願いとはいったいどういうことでしょうか。」
園子は嬉しさでいっぱいになり、
「そのお願いと申しますのは。」
といって、母の病気のこと、竹村家のこと、裁縫のことなどありのままに語ったが、その内容は話の順序もままならなかった。そして最後にこう言った。
「どうか一生のお願いでございます。私を哀れと思ってくださるなら、あの織物をひと巻き、くださいませんでしょうか?」
水谷は答えなかった。園子は言葉を継いだ。
「女の身でこのようなお願い、さぞお腹立ちでございましょうけれど。」
水谷はまだ答えない。
「お医者様によると、母はもう長くはないかもしれないとのこと。母は私のことだけが心残りなのです。どうか気の毒な母のため、この願いをかなえてくださいませんでしょうか。」
水谷は一言も発しなかったが、園子の最後の言葉を聞いて、なんと哀れな話だと思ったのであろう、一滴の涙をこぼした。その涙は園子にとって、千言万語にも勝る返答であっただろう。水谷は言った。
「あなたの願い、承りました。ただ、あの織物は甲斐の国の産物です。手配するのに二、三日はかかるでしょう。ご承知おきください。」
その言葉を聞いた園子は、まるで夢の中にいるような気持ちとなり
「この度は本当に。」
と答えることしかできなかった。水谷は言った。
「どちらへ届けさせましょうか。」
「私がいただきに上がりましょうか。」
「ほかになにか良い方法は?」
「私の母からの届け物として直接送っていただけますか。」
「それがよいでしょう。」
園子は
「御酒を一献差し上げたいのですが、いかがでしょうか。」
と問うたが、水谷は答えた。
「このような場所でゆっくりしていれば、あとあとお互いに余計な面倒があるかも知れません。酒はどこでも飲めましょう。今日はこれにて。」
園子も無理強いはせず、水谷が出てゆくのを見送った。
水谷は口数の少ない人だが、温和な人物であった。園子にとっては慈悲の心のあふれる恩人であった。園子は彼を尊敬するとともに、その心には思慕の念が生まれていたことだろう。
あとで園子は、自分のあんなふるまいを見て無礼な女と思われなかったか、自分の言葉に失礼がなかったか、この事はこう言えば良かったのではないか、あの事はこうしておけば良かったのでは、などと、女心の常としてそう思わずにいられないのだった。
花瓶にさした水仙花、柱にかけた短冊、広くはないが小綺麗な部屋、それが竹村家での園子の部屋である。例の病気といって引きこもっている園子は心の内で、今日はもう三日目、水谷様はどうされただろう、手紙を送ったら、催促と思われるだろうか、自分から訪ねてしまったら、軽率と言われてしまうだろうか。母の病気のお加減はいかがだろう、自分のことを案じてくださっているだろうけれど、私のこの心配事はご存じないはず。そんなことを園子はつれづれと思いつつ過ごしていた。
そのとき取次の者が紙の包みを持ってやってきた。部屋を出ていくのを待ってから開いてみると、あの織物だった。園子は、水谷様、と心のうちでつぶやき、手を合わせた。
園子は今度こそ、と昼夜の別もなく急いで縫い上げ、主人に見せると、主人はことのほか喜んだ。そうこうするうち、くだんの知事から急いで派遣してもらいたい、と連絡があった旨を主人は園子に伝えた。園子の喜びはどれほどであったろう。園子は急いで家に帰り母に伝えると、母の喜びようもまた計り知れないものだった。
少し暖かい陽気となった。母の病気も快復し、園子は母と共に出発することとなった。園子はその旨を水谷に書き送った。
水谷と別れてからは何日もたつけれど、園子はそれ以来一度も彼を訪ねたことはなかった。訪ねないだけでなく、お礼状さえ送っていなかった。それは人目をはばかってのこと、世間の目を考えてのことだった。手紙を送るのは、今回のその手紙が初めてなのだった。その手紙さえ、出立の日を知らせるのみで、余計なことは記さなかった。ただ、お目にかかれないのは本当に心残りであるとだけ書き添えた。
その日がやってきた。新橋の停車場にゆくと、水谷がそこにやって来ていた。園子はそれに気づくと歩み寄り、なにも言わずに涙ぐむのだった。水谷も黙って一礼するのみだったので、園子の母は知人の一人かと思っただけであった。
汽車が走り出そうとしていた。さようなら、水谷様。さようなら、園子様。ふり返る園子。それを見送る水谷。そのとき汽笛が鳴り、惜別の想いを映すかのように、長く響き続けた。
(明治二十三年一月「しがらみ草紙」)
*現代語訳:五十嵐哲也
(注)翻訳にあたっては極力原文の意味をくみとるよう留意しましたが、「(原文)みめかたちハたすくれたり → (訳文)容姿もすぐれた娘であった」のように原文にない単語「娘」を加えるなど、読みやすいように言い換えをした表現などがあることをご了承ください。また他、スマホ等での読みやすさを考慮して、改行のあとには行間を少し開け、またあきらかな場面転換の場所ではさらに行間を空けるよう表記しました。その他、古文の文法知識の不足などによる誤訳もあるかと思いますがご容赦ください。著しい間違いなどはご指摘いただけると助かります。
<解説にかえて>
小説『甲斐絹』は、歌人、国文学者としても知られる落合直文(おちあい なおぶみ、1861 - 1903)によるもので、森鷗外が主宰した月刊の文芸雑誌「しがらみ草子」で1890年(明治23年)1月に発表されました。
この作品の存在はこれまでシケンジョでも把握していませんでしたが、昨年2023年秋に開催されたFUJI TEXTILE WEEKの企画展『甲斐絹をよむ』の準備中、写真家の川谷光平さんが作品づくりのためのリサーチのなかで見つけてくれました。
現在でも小説『甲斐絹』は、『明治文學全集44』(筑摩書房)や、『落合直文著作集 2巻』(明治書院)で読むことができます。(ちなみに『明治書院』の社名は落合直文による命名で、初代編集長は彼の門下にいた与謝野鉄幹だったそうです。)
作品では、甲斐絹がヒロインの運命を左右する重要なアイテムとなり、また仄かな恋心をいだいた相手と出会うきっかけにもなっていて、作品中でも物語の重要な鍵となっていました。
このように『甲斐絹』そのものが中心となった文学作品というのは、この「文学の中の甲斐絹」シリーズで紹介している作品の中でも唯一無二の存在。
甲斐絹の歴史上、また山梨の歴史にとっても、非常に重要な作品といえるでしょう。
ここからは、作品の背景や描写を補足する情報をいくつかご紹介したいと思います。
「かの御召物ハしま柄、地合、いと美麗なり」
園子が竹村氏から渡された甲斐絹について、原文ではこのように表現されていて、それが美しい縞甲斐絹だったことが分ります。
また竹村氏はそれで「寝衣(しんい)」を作るように園子に依頼しました。「寝衣」はつまり和装の「寝間着、寝巻」、あるいは寝間着として使われる「浴衣」と考えられます。
甲斐絹がそうしたものに使われたという記述は、フィクションの中の例ではありますが、初めて知ることができました。
ふつう寝間着は木綿などで作られることが多かったようですが、和装の時代には身分の高い人は白絹を寝間着にしていたそうで、この小説のように裕福な主人が甲斐絹で寝衣を作るということは実際にあったのかもしれません。
甲斐絹に落ちる涙
物語の序盤のハイライトといえるのが、園子が渡された甲斐絹を間違えて裁ってしまい、甲斐絹のうえに幾つもの涙をこぼすシーンです。
この小説の発見者として先ほどご紹介した写真家の川谷光平さんの作品は、このシーンにインスパイアされたもので、企画展『甲斐絹をよむ』で展示作品のうちの2点として制作されました。
川谷さんの作品のなかで園子の落とした涙のつぶは、よく見るとコンタクトレンズです。
川谷さんは、この物語をモチーフにした写真作品を作るにあたって、130年以上たった2023年の世界でこの物語を読み取ったという印を込めたと話してくださいました。
光を受けて涙のつぶが甲斐絹以上にキラキラと輝いて見えます。
園子の呉服店めぐり
中盤では、裁ち間違えてしまったのと同じ甲斐絹がどこかで売ってないかと、園子が「大丸」「越後屋」「白木屋」を探し回るシーンがありました。
「大丸」「越後屋」「白木屋」は、江戸時代から「江戸三大呉服店」と呼ばれた老舗で、明治23年当時も反物を探す場所としては東京でもトップ3といえる大きな呉服店だったでしょう。
園子が甲斐絹を求めて走り回ったのは、作品の中に登場する地名「上野」「不忍池」「新橋駅」から、日本橋周辺にあった店舗だろうと推測できます。
「大丸」は当時の大丸呉服店で、現在は大丸松坂屋百貨店が経営する大丸東京店、「越後屋」は当時の三井越後屋呉服店、現在の日本橋三越本店と思われます。
「白木屋」は江戸時代から続くも1967年に日本橋本店が東急百貨店となり現在その名は残りませんが、本店のあった場所はいまコレド日本橋になっています。
こうした最大級の呉服店三軒を探し回っても見つからないということで、甲斐絹を求めてさまよう園子の焦燥の度合いが察せられます。
「孝女」モチーフ
この小説の大まかな筋は、母親想いの園子が、間違えて切ってしまった甲斐絹の代わりを得るため、勇気を出して訪ねた水谷のおかげで救われ、無事に親孝行を果たすことができたという、親孝行ストーリーとも言えるものでした。
現代の感覚からすると、ここまで母のことばかり考えている園子が不思議に思えるくらい親孝行が園子のモチベーションの核になっています。
ところで落合直文の代表作は、当時世界的にも広まった作品『孝女白菊の歌』といわれており、それは主人公の白菊という娘が、行方不明の父を探す旅に出るという父親孝行娘のについての詩編だそうです。
その『孝女白菊の歌』は『甲斐絹』の前年、前々年に書かれたとされ、『甲斐絹』での園子の母親孝行ぶりを読むと、この二作はもしかしたら白菊と園子が対になった孝行娘シリーズと言えるものだったのではないかという想像もできます。
あるいは当時の修身教育では、親孝行が倫理道徳の中心とされていたそうなので、このように親孝行の要素があるのはごく当たり前のことだったのかも知れません。
「甲斐絹」の当て字が広まった時期
「甲斐絹」というのは明治時代に生まれた当て字です。それまでは「海気」「海機」「改機」「加伊岐」などの様々な当て字のほか、片仮名で「カイキ」とされることもあったそうです。
『創立70周年記念誌』(山梨県工業試験場 )によると、その中で最も多く使われたのが「海気」で、明治30年頃までは地元でもこれを使い、また県文書統計も明治40年まで「海気」を使用していた、という記述があります。
今回見つかった『甲斐絹』が書かれたのは1890年(明治23年)ということなので、その頃に県外でも一般に「甲斐絹」の表記がある程度広まっていたことを新たに示す証拠となりました。
また、もしかすると当時の著名人である落合直文が小説のタイトルに『海気』ではなく『甲斐絹』を選んだということで、甲斐絹が甲斐の国の物産であることが広まり、一般に「甲斐絹」の表記を広める推進力になったかもしれないと想像することもできます。
駅での別れ
後半は、窮地に陥った園子の救い主として登場する「水谷様」への恋心もうっすらと描かれ、物語のラストの場面は、文字数はきわめて少ないながら、新橋駅での二人の感動的な別れのシーンとなっていたのが印象的でした。
ここで新橋駅について日本の鉄道の歴史をひもといてみると、日本初の鉄道が新橋~横浜間で開通したのが1872年(明治5年)、新橋~国府津間(小田原の手前)まで延びたのが1887年(明治20年)、そして新橋から国府津の先まで開通したのは1889年(明治22年)の新橋~神戸の全線開通の年になっています。(ちなみに上野~青森の東北線開通は1891年(明治24年)です。)(『日本の鉄道創世記』河出書房親書より)
園子の赴任先は、作中では「某縣(県)」としか説明はありませんが、新橋駅での別れのラストシーンがあのような切ない別れの描写だったので、ある程度遠い場所だったと思って良いでしょう。
新橋からの鉄道が十分に遠い土地(小田原以遠)まで延びたのは1889年(明治22年)なので、『甲斐絹』の1890年(明治23年)というのは、その直後といえる時期に書かれたということが言えそうです。
駅での別れの名シーンは映画や小説の中でたくさん描かれてきたと思いますが、『甲斐絹』の事例は、その中でもかなり初期の部類であると言えるのではないでしょうか。
そしてもしかしたら、このような別れのシーンの原型のひとつになっていった可能性もあるのでは、と想像が広がります。
駅での別れというモチーフで個人的に思い出されるのが、伝説のブルースマンと言われるロバート・ジョンソン(1911 - 1938)の『Love in Vain』(1937年録音)という曲です。ザ・ローリング・ストーンズによるカバーが特に有名です。
歌詞を日本語にするとこんな感じです。
・ ・ ・ ・ ・
『Love in Vain』 / Robert Johnson
『むなしい恋』/ロバート・ジョンソン
駅まで彼女を見送りに行ったんだ
スーツケースを一つ持って運んであげた
ああ、恋が終わろうとしているときに
言葉なんて出てきやしない
僕の恋は終わってしまうんだ
汽車が駅にやってきたとき
僕は彼女の瞳を覗き込んだんだ
ああ、切なかった、もう切なくて
涙を流すことしかできなかった
僕の恋はもう終わってしまうんだ
列車が駅を出ていってしまったあと
二つの灯りが点っていたんだ
青い灯りは僕の悲しみで
赤い灯りは僕の心だった
そうして、僕の恋は終わってしまった
ああ、ウイリー・メイ
ああ、ウイリー・メイ
僕の恋はむなしく終わってしまった
(日本語訳:五十嵐哲也)
・ ・ ・ ・ ・
『甲斐絹』のラストシーンとシチュエーションは若干違いますが、駅から走り去る列車が二人を無情に引き離すときの、やるせなさ、せつなさは、とても近しいような気がします。
また男性のほうが残って、旅立つ女性を見送るというパターンも一緒です。
『甲斐絹』では汽笛、『Love in Vain』では信号灯という鉄道の備品が、感情を表現する演出の小道具になっているのも共通しています。
ロバート・ジョンソンの歌が録音されたのは今からもう約90年近く前で、もはやクラシック音楽といえるくらいの長い歴史を経ていますが、驚くべきことに『甲斐絹』での駅の別れのシーンは、さらに47年、約半世紀も前(!)にさかのぼります。
このことからも『甲斐絹』のラストの駅での別れのシーンは、かなり早い時期の事例だったことが実感できるのではないでしょうか。
以上、落合直文の『甲斐絹』の現代語訳と、作品を味わうための解説をいくつかご紹介しました。
甲斐絹の中の文学シリーズ、次回は作品に描かれた甲斐絹の風景をご紹介する予定です。
どうぞお楽しみに。
[甲斐絹 関連ページ]
2024年 4月25日 文学の中の甲斐絹 ⑥甲斐絹の風景2024年 2月19日 文学の中の甲斐絹 ⑤現代語訳で読む、落合直文の小説『甲斐絹』
2024年 1月24日 文学の中の甲斐絹 ④甲斐絹の用途
2023年 10月4日 文学の中の甲斐絹 ③甲斐絹の色彩
2023年 10月4日 文学の中の甲斐絹 ②甲斐絹のオノマトペ辞典
2023年 10月3日 文学の中の甲斐絹 ①文人たちが書いた甲斐絹
2022年 10月21日 DESIGN MUSEUM JAPAN 山梨展「甲斐絹」千年続く織物 “郡内織物”のルーツ
2014年 1月17日 甲斐絹ミュージアムより #10 「白桜十字詩」
2013年12月24日 甲斐絹ミュージアムより #9 「この松竹梅がスゴイ!」
2013年11月15日 甲斐絹ミュージアムより #8 「今週の絵甲斐絹3 ~松竹梅~」
2013年10月31日 甲斐絹ミュージアムより #7 「今週の絵甲斐絹2」
2013年10月25日 甲斐絹ミュージアムより #6 「今週の絵甲斐絹1」
2013年 9月27日 甲斐絹ミュージアムより #5/84年後に甦った甲斐絹
2013年 9月21日 甲斐絹ミュージアムより #4/甲斐絹展が始まります!
2013年 6月28日 甲斐絹ミュージアムより #3 シャンブレーの極致!玉虫甲斐絹
2012年 4月27日 甲斐絹ミュージアムより #2
2012年 4月13日 甲斐絹ミュージアムより #1
(五十嵐)