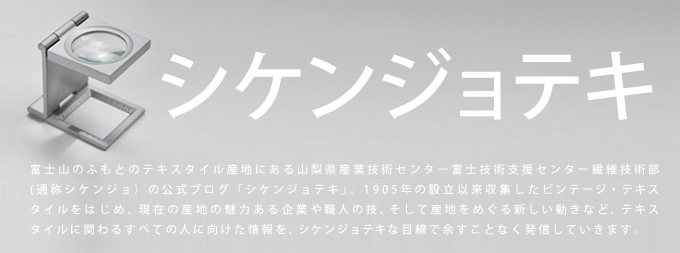以前ブログで紹介した郡内の織物にフォーカスした展示会「郡内直送織物展」の会場の模様を撮影してきたのでご紹介します。
この展示の企画をしたナノリウムは富士山のすそ野の森の中にひっそりとたたずむギャラリーカフェなのですが、この展示会では県内外からのお客さんも多く、予想以上の反響にオーナーの中植さんも驚いていました。
それでは、郡内産地の作る織物の世界をご覧ください。
こちらは会場の様子。
郡内直送織物ではおなじみのほぐし織りの傘は、天井から吊り下げられており、まるでランプシェイドの様でした。
織物がつくられる現場を想像できるインスタレーション(空間演出)。
織物だけ売るのではなく、織物の裏側ににあるストーリーをモノと一緒に持って帰ることで、
お客さんの満足度も違うようでした。
こちらも郡内ではおなじみの仏間用座布団(通称:テラザブ)。
座布団の他にも、ペンケースやPCケースなどの商品展開もありました。
絢爛豪華!!
産地から出た端切れを使ったインスタレーション。
影がとてもきれいでした。
普段は捨ててしまう織物のミミも、扱い方次第では立派なオブジェに変わっています。
こちらは電子基板をテキスタイルにしたプロダクト「KIBAN」シリーズ。
金襴緞子の技術を使い柄をデザインしているので、プリントでは出すことのできない立体感と輝きが特徴です。
珍品、紗織りのネクタイ!!
紗織りとはタテ糸をヨコ方向にも動かしながら織る、とても難しい織り方です。
紗織り独特の透け感で涼しげな夏のビジネスシーンにもってこいなネクタイです。
上の写真はリネンやシルクを組み合わせた、カワイイネクタイ。
女の子でも使えそうです。
綿のネクタイ!?
とっ、思いきや、100%シルクネクタイ!
会場にはひっそりとシケンジョで開発した「銀染め」の糸も置かせてもらいました。
シャットル織機のシャトル。
店では売っていないような素敵な傘が沢山ありました。
hengenは山梨で生まれた天然の国産絹を使った「甲斐絹」によるブランドです.
上の写真は国産のシルクを使ったストール。
写真:右)ジャカード織機に使用する、紋紙
写真:左)シケンジョで研究している、濡れ巻き整経の途中工程の経玉。
100%シルクのオーガンジ―ストール。
青とオリーブグリーンの糸で織られており、先染めならではの美しい色合いが素敵でした。
izumi okuno
日本の一地方の織物産地から発信する小さな展示会ですが、なにか世界に打ち出せるような大きな魅力を感じました。この様な産地発の展示が同時多発的にいろんなところで生まれれば、郡内織物産地がもっともっと魅力的な産地になっていくのではないでしょうか?