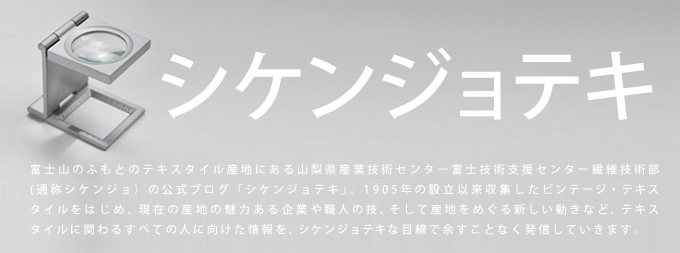2025年初夏、タイ王国のタイ繊維産業開発機構(THTI)からお招きいただいて、2025年6月5~10日の6日間、タイを訪問してきました。
タイで山梨のハタオリを伝え、タイのハタオリ産地をめぐる、ハタオリトラベル in タイ王国を今回からシリーズでお伝えします!
※写真は一部を除きTHTIから提供いただいたもので、許可を得て掲載しています。
渡航依頼の内容は、2025年6月6日と9日、タイのチェンマイ(北部)とウドンタニ―(東北部:イサーン地方)で講演し、テキスタイル事業者のみなさんに郡内織物の紹介をすること。
その他に、タイの織物、特に手織りの手工芸的な織物産業を視察させてもらいましたが、今回は、講演がどんな様子だったかを、写真でご紹介します。
上の写真は、現地でお世話になったタイ繊維産業開発機構(THTI)の皆さんです。
THTIは、タイ政府が1996年に設置したタイの繊維産業を支援する政府機関。タイの国立シケンジョのような存在です。
タイテキスタイル産業振興会、タイ繊維研究所、などとも訳されることがありますが、ここではタイ王国大使館のスタッフの方からいただいた和訳名称を使用しています。
ちなみにタイでは普段ニックネーム(タイ語でチューレン)で呼び合う習慣があるそうで、スタッフの皆さんのお名前はいずれもチューレンで、本名は別にあります。
そもそも今回、タイからお招きがあったのは、2023年と今年2月、THTIの皆さんによる郡内織物産地の視察があったことがきっかけでした。
上の写真が、2月の訪問時の写真です。THTIのPunnaratさん、PPさんらが来日していました。
今回シケンジョの五十嵐とともにお声がかかったのは、舟久保織物の舟久保勝さんでした。
舟久保さんはバンコク、五十嵐はチェンマイとウドンタニ―、それぞれタイの遠く離れた3か所で講演をしてきました。
バンコク/舟久保織物さん編
6月4日にバンコクにて、ほぐし織を中心に舟久保織物さんのものづくりを紹介する舟久保勝さんの講演会が行われました。
タイには「絣(かすり)」の織物、マットミー(タイのイカット)はありますが、ほぐし織のように、型紙(スクリーン印刷)で糸に柄をつける技法はないようです。
受講者の表情から、舟久保さんの生地やほぐし織の技術に興味津々であることが伺えます。
★マットミー(mudmee/มัดหมี่ มัดマット=縛る、หมี่ミー=細い絹糸などの意)。
イカット(ikat)という言葉が世界的にアジアの絣織物をさす言葉として広まっていますが、イカットはもとはインドネシアの絣の名前からきているそうです。
ちなみに舟久保さんとは日程はかぶっていますが場所が違うので、二人は別々のスケジュール。残念ながら現地で会うことはありませんでした。
チェンマイ編:五十嵐講演
さてシケンジョから招かれた五十嵐、最初の講演は、2025年6月6日(金)、タイ北部のチェンマイにあるThe Empress Hotelで行われました。
講演会場はこんな感じです。
上の写真の衝立に書いてあるのは、「タイと海外のデザイナーによるタイの織物工芸品の発展活動」、「伝統の再発見と持続可能な未来をつなぐデザイナー滞在プログラム 2025」という言葉。
6月4~6日の3日間、このホテルで地元のデザイナー、織物事業者を対象に、このような3日間の研修プログラムが開催されていて、自分はそのうちの講師の一人として招かれたのでした(現地に着いてから知りました)。
山梨から持って行った生地や商品を置かせてもらったところ、チェンマイのデザイナー、職人、経営者の皆さんは興味津々で見てくれました。
下の青い画面が用意したプレゼン資料の表紙です。タイ文字は翻訳ツールのお世話になりました。
お話しした内容は、山梨での地域の伝統産業の歴史文化と、近年の取り組みやデザインの事例紹介でした。ルーツを踏まえて産地がどのように変化し、挑戦を重ねてきたか、またシケンジョではそれをどうサポートしてきたかをお伝えする前半と、テキスタイル開発をお伝えする後半の二つで、90分ほどの講演を行いました。
山梨の織物のことを知るのはきっと生まれて初めてのことだったと思います。皆さん、真剣に聞き入ってくれていたようです。
日本語に堪能な通訳さんが頼もしかったです。
講演中も山梨のハタオリ商品が回覧され好評を博していました。
講演後は、山梨の織物やそのデザイン、研究開発について、皆さんから沢山の質問が寄せられました。
そして最後は皆さんで記念撮影。
記念撮影用の背景ボードや、ハッシュタグやロゴマークのプラカードがちゃんと準備されていて、こうしたイベントをSNSで発信することの重要性が浸透していることを感じました。
ウドンタニ―編
そして次の講演は2025年6月9日(月)、場所は東に400㎞ほど離れた、イサーン地方のウドンタニー。会場はアンマン・ユニークホテルです。
ウドンタニ―周辺のタイ東北部は手織りシルクの産地として知られています。
THTIのNokさんが熱いトークで盛り上げて、会場を温めてくれました。
あとでNokさんが何を言っていたのか通訳さんに聞いたら、「日本から来た五十嵐センセーは興味津々で色んなことを質問してくるんだ」、というような紹介をしてくれていたそうです。
それを聞いている皆さん。”微笑みの国”と呼ばれるだけあり、みなさん優しい笑顔です。
チェンマイとは違う通訳さんがサポートしてくれました。
生地に触れると、皆さん生き生きとして楽しそうです。
そして講演後は、やはり記念撮影タイム。
集合写真のあとは、個別の記念撮影大会がはじまりました。
記念写真の笑顔から推測すると、皆さん興味を持って聞いてくれたようです。2回の講演はなんとかお役目を果たすことができたかと思います。
そしてもうひとつ、講習のなかでは、この映像も皆さんに見ていただきました。「ハタオリマチノキオク」という映像と音楽の作品。
 |
| この画像をクリックすると、YouTubeの「ハタオリマチノキオク」が別ウィンドウで開きます。 |
「ハタオリマチノキオク」は、写真家の濱田英明さんの映像による富士吉田の風景、音楽家の田辺玄さん森ゆにさんによる楽曲「LOOM」が一体となった作品です。
チェンマイ、ウドンタニ―のどちらの講演でもこれを途中で上映させてもらいましたが、どちらの会場でも終わったあとに拍手が鳴り、参加者の皆さんが笑顔を見せてくれたことが感動的でした。
タイでは、機械式織機による工業的な織物生産も盛んですが、養蚕や手織りによる手工芸的な織物生産も大きな産業として残っています。
今回参加させていただいたプログラムは、手工芸的な織物産業をグローバル市場に向けて発展させていくため、若いデザイナーたちの育成を政府が後押しするものとして行われたものでした。
チェンマイとウドンタニ―で出会った受講者の皆さんは、みな真剣な目で山梨の織物から学び、生地を手にして目を輝かせていました。彼らの挑戦に少しでもお役に立つことができたら幸いです。
そして自分にとっても、タイで見た織物とその生産風景は、とても刺激的なものでした。
次回は、講演以外の時間のほとんどをTHTIの皆さんがつきっきりで案内してくれた、タイの織物産地の様子をご紹介したいと思います。ぜひお楽しみに!
(五十嵐)