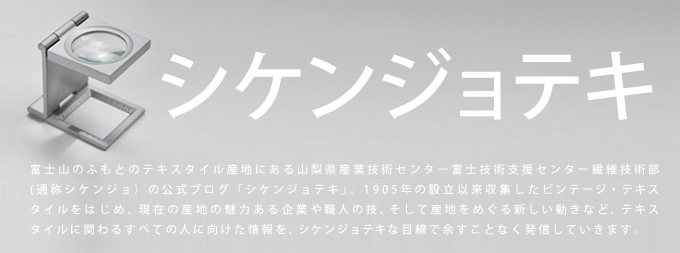これは最高級のウェディングドレスに使われる生地。
21中×2本という極細のシルクを高密度に織り上げ、「鏡のようなサテン」と謳われた濡れ巻きならではの光沢を見せています。
「濡れ巻き」というのは、山梨県織物産地に独特の伝統的な整経技法です。濡れ巻き整経では、染色する前に経糸本数×整経長の糸の束を作り、経玉(へだま)という糸の塊を作ります。経玉にすることで、糸を染色屋さんへ持って行くときなど移動の際も糸が傷まず、またコンパクトなのでこのままの形で保管するにも適しています。
 |
| 経玉(へだま) |
昭和30年代まではほとんど全てといっていいくらい普及していた濡れ巻き整経ですが、いまでは職人の高齢化などでわずかに残っているのみとなっています。
濡れ巻き整経で作られたシルクサテンは、普通の機械式の部分整経機で作られたものと比較しても光沢度が高いという結果が、シケンジョで行なった研究によって明らかになっています。

* 光沢度の比較 *
濡れ巻き整経と部分整経を比較するため、整経方法だけを変えて同じ原糸をつかって同じ釜で染色し、同一織機で製織した生地を計測した。測定角度は、光沢度を計測する際の生地の角度を経糸方向から22.5度ずつ変化させた値。タテ出しサテン組織のため、経糸方向のときに最も光沢度が高くなっている。『濡れ巻き技術に関する調査研究』(山梨県富士工業技術センター)
思えばお蚕さんが吐き出した糸はとうぜん100%天然素材です。天然繊維でこのような宝石のような光沢が生まれるなんて、不思議じゃありませんか?
シルクは、19世紀にビスコースレーヨンが発明されるまで、数千年の長い年月にわたって、世の中で唯一のフィラメント糸でした。このシルクを使って最高の光沢をもたらすように発達してきた濡れ巻き整経の技。シルクの魅力を最大限に発揮する、ヤマナシ産地ならではの輝きです。
この生地は濡れ巻き整経でシルクサテンのドレス地を製造する日本で唯一の織物企業、宮下織物(株)で作られています。
ヤマナシ産地では、他にも濡れ巻き整経で生地を作り続ける機屋さんがありますので、またいずれご紹介したいと思います。

〔おしらせ〕
宮下織物さんも参加しているTN展が、11月6日(火)~7日(水)に東京・青山で開催されます。
ここでご紹介した濡れ巻きサテンも、「品番2300」という名前で出展されますので、興味のある方は現物を見に行ってみてはいかがでしょうか?
日程 平成24年11月6日(火)~7日(水)
会場 スタジアムプレイス青山 (〒107-0061 東京都港区北青山2-9-5)
(五十嵐)