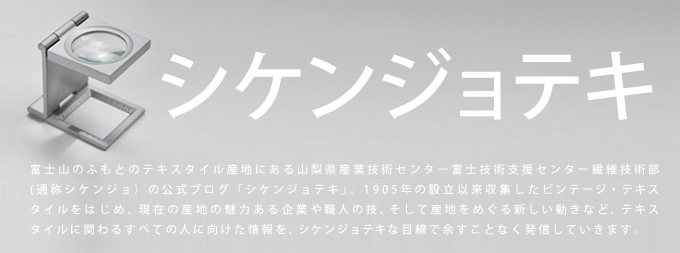今回は、前回紹介したサテンの描き方で作られる
いろいろなサテンを比べてみてみようと思います。
まずはその前段として、組織のサイズについて考えてみましょう。
組織のサイズについて
上の図は、組織サイズと、経糸と緯糸の交差の様子を示しています。
青い緯糸が、黒い経糸の上を通る(=浮く)サイクルが、組織サイズと同じことが分かります。
組織のサイズが変わると、できあがる生地の特徴は、大きく次のように変わります。
サイズが大きくなると、緯糸と経糸の表から見える比率の差が大きく(片方が目立つように)なり、
また糸の交差の間隔が広くなるので、構造が緩くなり、柔らかい生地になります。
構造が緩くなると、緯糸の密度をより高くする(打ち込みを上げる)こともできるようになります。
この関係を、下の図のようにまとめてみました。
上図では、横軸が組織のサイズ、縦軸が「□」と「■」が組織図に占める比率になっています。
縦軸・横軸にそって移動していくことで、組織の性質や特徴は、
縦軸・横軸にそって移動していくことで、組織の性質や特徴は、
図の左と上に書いてある矢印であらわしたように変わっていきます。
織物を設計する職人は、こうした効果を考えて織物組織を選んでいるわけです。
ちなみに、中ほどのサイズ=5のところで示したのは「増点法」という変化組織の作り方です。
「□」と「■」の比率を段階的に変えることで、グラデーション表現に使われます。
考えられるあらゆる組織をこの図にプロットすることができますが、
組織の柔らかさや緯糸密度の限度などの関係は、組織点「■」の配置によっても変わるので、
必ずしもこの図のようにならない場合があります。
この図では、組織サイズと「□」と「■」の比率の関係について、
おおよその傾向を示していると考えてください。
重口と軽口について
先ほどの図で、上に行くほど組織図の中で
白い「□」が多く、下に行くほど「■」が多くなっていました。
「■」は、織機が経糸を持ち上げる箇所をあらわすので、
図の下の方にある「■」が多い組織は、織機が緯糸を織り込むときに
持ち上げなくてはならない経糸の数が多い組織ということで、
つまり織機にとって「重い」組織になります。
このため、「■」が多い組織を「重口(おもくち)」、
逆に「□」が多い組織を「軽口(かるくち)」と呼びます。
「口」というのは、組織のうちの横一行ぶん(緯糸1本ぶん)を指します。
緯糸を織り込んでいるときのある一瞬をとらえて見ると、
組織のある1行のうち、「■」にあたる経糸が持ち上げられています。
その時に、それが「■」の方が少なければ軽口、「■」の方が多ければ重口ということになります。
サイズと飛び数のバリエーション
下の数字は、繻子織りのサイズと、飛び数の組み合わせ例を示しています。
(前回もご紹介した図です)
では、ここで実際に16枚までのパターンを全て並べてみてみましょう。
こうしてみると、繻子織りと言っても、いろいろなパターンがあることが分かると思います。
ただし、生地の見た目は、経糸・緯糸に使う糸の素材・太さ・密度によって変わるので、
必ずしもここで紹介した写真と同じ見た目になるとは限りません。
とくに今回の実験では、4枚~7枚は他の枚数のときより緯糸密度を粗く織っていますので、
黒い経糸の影響が若干強く見えていることにもご注意ください。
4枚と6枚について
上の一覧で、4枚と6枚があったことを不思議に思った方がいるかもしれません。
じつは、4と6には、サテンの飛び数のルールを満たす数字がありません。
つまり、4枚と6枚の繻子組織は、これまでのルールでは存在できないのです。
しかし、世の中には4枚や6枚の綜絖をそなえた織機で織るときなど、
4枚や6枚のサイズで繻子組織を使いたい、という場合があります。
ここで紹介したのは、その時に繻子織りの代わりに使われる組織です。
4枚の方は、「破れ斜紋」と呼ばれます。 「斜紋」とは、綾織のことです。
「■」が45度の角度で接しているので、繻子織りのルールから外れていますが、
・経糸:緯糸の比が1:3で、片側の糸が目立つ組織
・綾織と違って、斜めの線が目立たない
という2つの点から、繻子織りの役目を果たすことができると考えられます。
6枚の方は、じつは前回説明した繻子織りのルール①、②を完全に満たしています。
ただ、飛び数が列ごとに{3飛び、2飛び、2飛び、3飛び…}と変化しているだけです。
6枚では、固定した飛び数の組み合わせは存在しませんが、
このように変化する飛び数を使えば、繻子織りを作ることができるというわけです。
こうした繻子組織を、「変則繻子」と呼びます。
変則繻子は、6枚だけでなく、6枚以上のあらゆるサイズで作ることができます。
次回は、今回示したいろいろな繻子組織どうしの関係、
そして変則繻子についてご紹介しようと思います。
お楽しみに!
(五十嵐)